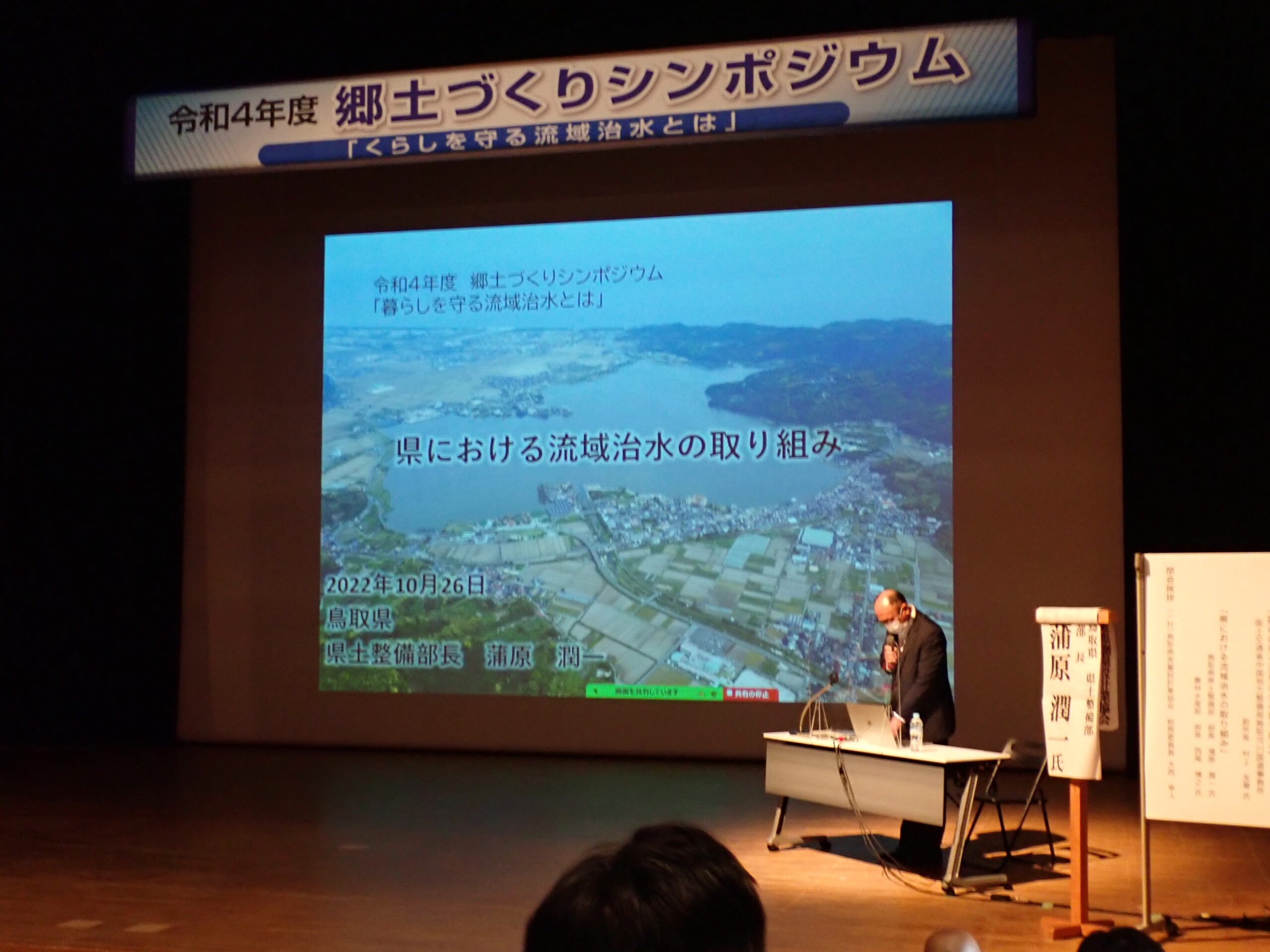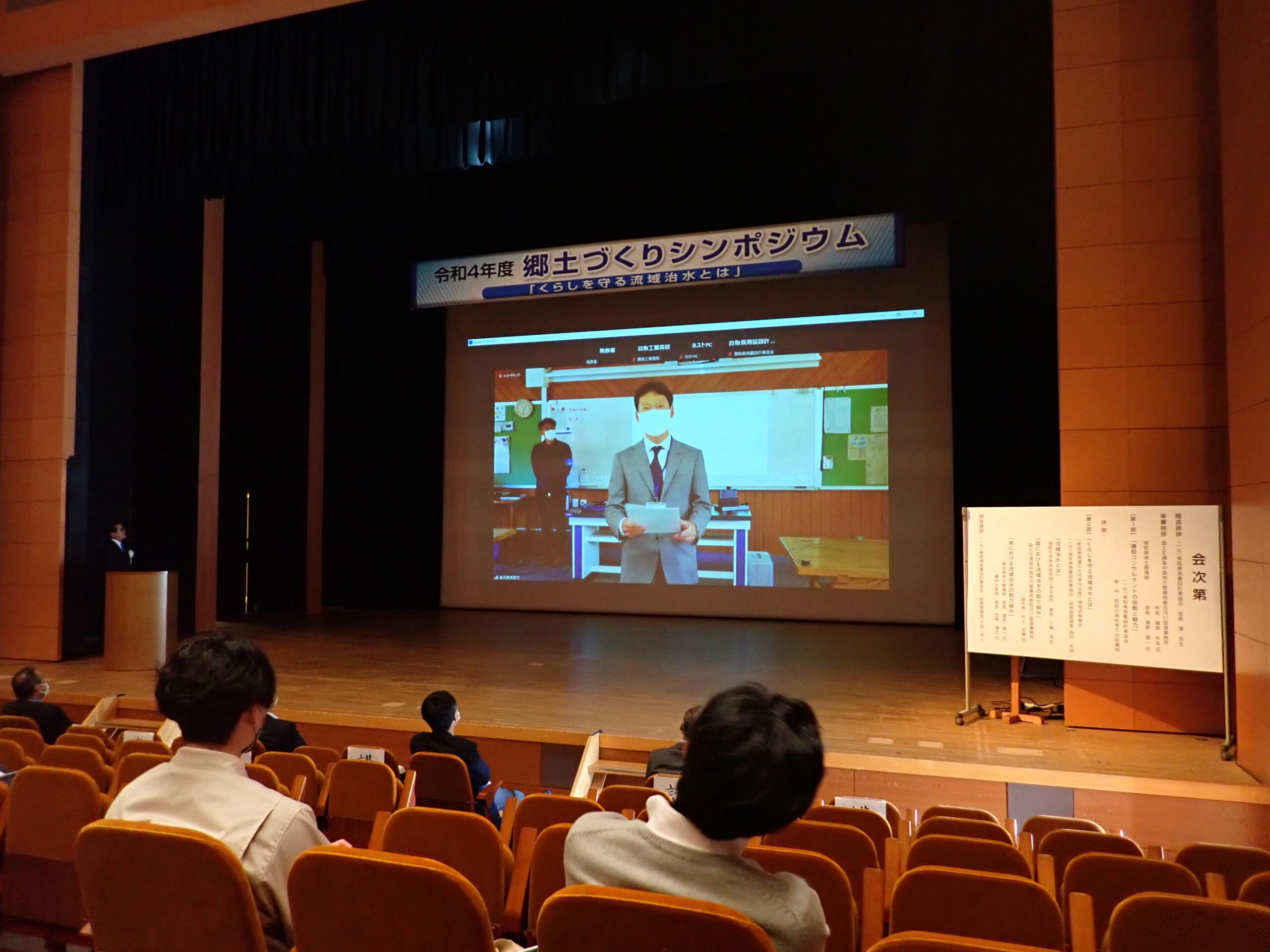どのように道路が作られるのだろう…?
みなさんは、設計ってどんな風に行っているのか、ご存じでしょうか。
例えば、直線の道路を作りたいところに自由に作れるかといったら、そうではありません。
高低差があったり、お家や田畑、動かすことの出来ない支障物があったり、、まずは工事をしようとしている現地の状況を知る必要があります。
ただただ、設計を行うだけではありません。
『基準に則って設計を行う』ことは、当たり前のことなのですが、全く同じ現場というものは一つとしてありません。
現場の固有条件や予算、そして地元や自治体の考え方など様々なことを考慮しながら設計していきます。
安全性、利便性、経済性、工事が可能か否か、、
たくさんの課題に向き合って、複数の計画を比較検討し、発注者や地元の方々に提案します。
提案する際に大事なことが、いかに分かりやすくプレゼンできるかどうかです。
計画を提案する際に、設計した計画図だけでなく、『どんな手順でどのように施工するのか』といった施工計画という作業を一緒に行います。
設計のうちの、ほんの一部分ではありますが、施工計画について、一緒に動画を観てみましょう(^^)
☆★ちなみにこの動画は、打合せの際に発注者がイメージしやすいようにと、弊社の設計部社員が作成したものです★☆